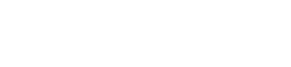発達障害という言葉を耳にする機会が増え、
「自分や周りの人の特徴と似ているかも?」と感じて、このページにたどり着いた方もいらっしゃるかもしれません。
政府広報オンラインの記事「発達障害って、なんだろう?」によると、発達障害は、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など、脳機能の発達に関係する障害です。これは病気ではなく、その人自身の「特性」として理解されています。発達の偏りがあることで、ものの感じ方や考え方、人との関わり方などに独特の傾向が見られ、日常生活や社会生活で困難さを感じることがあります。しかし、特性を理解し、適切な工夫や支援があれば、社会生活を送りやすくすることが可能です。優れた能力が発揮されている場合もあり、周りから見てアンバランスな様子が理解されにくいという特徴も指摘されています。
この記事では、発達障害の主な種類ごとの特徴、年齢や性別による現れ方の違い、診断やグレーゾーンについて詳しく解説します。ご自身の特性を理解し、より快適な生活を送るためのヒントを見つける一助となれば幸いです。
発達障害の定義と全体像
発達障害とは、生まれつきの脳機能の発達の仕方の違いによって、特定の能力の習得や社会生活への適応に困難さが生じやすい状態を指します。これは育て方や本人の努力不足によるものではなく、脳の構造や機能の偏りによるものです。
発達障害の特性は一人ひとり異なり、様々な現れ方をします。例えば、コミュニケーションが苦手な人もいれば、特定の物事に極めて強い興味を持つ人もいます。また、じっとしているのが難しい人もいれば、特定の科目の学習に困難を抱える人もいます。これらの特性は幼少期に現れることが多いですが、大人になってから社会生活で困難を感じて気づくケースも少なくありません。
発達障害の種類はいくつかありますが、それぞれが独立しているというよりは、特性が重複して見られることもよくあります。重要なのは、診断名にとらわれすぎず、その人がどのような特性を持ち、どのようなことで困っているのかを理解することです。特性を理解することで、本人や周囲ができる工夫が見えてきます。
発達障害の主な種類とそれぞれの特徴
発達障害は、主に以下のいくつかの種類に分類されます。これらの分類は、DSM(精神疾患の診断・統計マニュアル)やICD(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)といった国際的な診断基準に基づいています。現在は、特性の連続性を重視し、「自閉症スペクトラム障害」のように「スペクトラム(連続体)」という言葉が使われることが増えています。
主な種類としては、以下の3つが挙げられます。
- 自閉スペクトラム症(ASD): 対人関係やコミュニケーションの困難、限定された興味やこだわり
- 注意欠如・多動症(ADHD): 不注意、多動性、衝動性
- 限局性学習症(LD/SLD): 知的な発達に遅れはないが、特定の学習能力(読み書き、計算など)に困難がある
これらの特性は重複して現れることも少なくありません。例えば、ASDとADHDの両方の特性を併せ持つ人もいます。
自閉スペクトラム症(ASD)の特徴
自閉スペクトラム症(ASD)は、対人関係やコミュニケーションの困難さ、および限定された興味やこだわり、反復行動などが特徴とされます。以前は、千葉市立図書館の資料などでも触れられているように、自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害などが個別の診断名として挙げられていましたが、現在は特性の連続性から「自閉スペクトラム症」としてまとめられています。
ASDの対人関係・コミュニケーションの特徴
ASDの人は、非言語的なコミュニケーション(表情、声のトーン、身振り手振り)を読み取ったり、適切に使用したりするのが苦手な傾向があります。また、暗黙の了解や場の空気を読むことが難しく、言葉を額面通りに受け取りやすいという特徴も見られます。
具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 相手の冗談や皮肉が理解できず、真に受けてしまう。
- 相手の表情や声のトーンから感情を読み取るのが難しい。
- 自分の感情や考えを言葉で表現するのが苦手、または一方的になってしまう。
- 他者と視線を合わせるのが苦手、または視線が合いすぎる。
- 集団での会話に入っていくタイミングが分からない、または唐突に話始める。
- 曖昧な表現が苦手で、具体的な指示を好む。
- 雑談が苦手で、目的のない会話に 어려움을 느낄 수 있다。
ASDの限定された興味・こだわり行動の特徴
ASDの人は、特定の物事に対して非常に強い興味や関心を持ち、深い知識を持つことがあります。また、特定のルーチンや手順にこだわり、変化を嫌う傾向が見られます。感覚過敏または鈍感といった感覚特性もよく見られます。
具体的な例としては、以下のようなものがあります。
- 特定の分野(電車、恐竜、アニメなど)に異常なほど詳しい。
- 同じ本や映像を繰り返し見ることを好む。
- 毎日決まった順番や方法で物事を行うことにこだわる。
- 予定や環境の変化に強い不安を感じたり、パニックになったりする。
- 特定の音や光、匂い、肌触りなどに極端に敏感(感覚過敏)または鈍感(感覚鈍感)。
- 手をひらひらさせる、体を揺らすなどの反復行動(常同行動)が見られることがある。
これらの特性は、その人の個性や得意なことにつながることもあります。例えば、特定の分野への強いこだわりは、専門的な知識やスキルとして仕事に活かされることもあります。
注意欠如・多動症(ADHD)の特徴
注意欠如・多動症(ADHD)は、「不注意」「多動性」「衝動性」といった特性が特徴です。これらの特性の現れ方によって、主に「不注意優勢型」「多動・衝動性優勢型」「混合型」に分類されることがあります。必ずしも全ての特性が強く現れるわけではなく、年齢によって現れ方が変化することもあります。
ADHDの不注意の特徴
不注意の特性が強い人は、集中力を持続させることが難しかったり、細かいミスが多かったりする傾向があります。
具体的な例としては、以下のようなものがあります。
- 学校の授業や仕事中に、集中力が続かず上の空になってしまう。
- 人の話を最後まで聞くのが難しく、聞き漏らしが多い。
- 忘れ物やなくし物が多い(鍵、財布、携帯電話など)。
- 頼まれたことややるべきことを忘れてしまう。
- 物事を計画通りに進めたり、順序立てて行ったりするのが苦手。
- 締め切りを守るのが難しい。
- 片付けや整理整頓が苦手で、部屋やデスクが散らかりやすい。
- 細かい不注意によるミスが多い(書類の誤字脱字、計算間違いなど)。
- 一つの作業を長時間続けるのが難しい。
ADHDの多動性・衝動性の特徴
多動性や衝動性の特性が強い人は、じっとしているのが難しかったり、思いついたことをすぐに行動に移してしまったりする傾向があります。
具体的な例としては、以下のようなものがあります。
- 授業中や会議中に席を離れたり、そわそわしたりする。
- 手足をもじもじさせたり、貧乏ゆすりをしたりする。
- 過度におしゃべりをする。
- 順番待ちが苦手で、列に割り込んでしまう。
- 人の話の途中で遮って話始めてしまう。
- 考えずに行動に移してしまい、失敗することが多い(衝動買い、衝動的な転職など)。
- 危険なことでも、後先考えずに行ってしまうことがある。
- カッとなりやすく、感情を抑えるのが難しい。
多動性は成長とともに目立たなくなることがありますが、内心の落ち着きのなさ(ソワソワ感)として残ることもあります。衝動性は、対人関係のトラブルや金銭的な問題につながることもあります。
限局性学習症(LD)の特徴
限局性学習症(LD: Learning Disorder)は、全般的な知的な発達に遅れはないものの、読む、書く、計算する、推論するといった特定の学習能力のうち、いずれかに著しい困難がある状態を指します。特定の学習領域に限定されるのが特徴です。
LDの読み書きの困難さ
読み書きに困難がある場合、文字の形や音の結びつき、単語や文章の構造の理解などが難しくなることがあります。
具体的な例としては、以下のようなものがあります。
- 文字の形を認識するのが難しい(「ろ」と「る」、「わ」と「ね」など)。
- 文字と音を結びつけるのが難しい(音読がスムーズにできない)。
- 単語の読み方を覚えるのに時間がかかる。
- 文章を読む速度が非常に遅い。
- 文章を読んでも内容を理解するのが難しい。
- 文字を正確に書くのが難しい(鏡文字、誤字脱字が多い)。
- ひらがなやカタカナ、漢字を覚えるのに時間がかかる。
- 文章を構成して書くのが苦手。
- 句読点を適切に使えない。
LDの計算・推論の困難さ
計算や推論に困難がある場合、数の概念の理解や計算手順の習得、図形や文章問題の理解などが難しくなることがあります。
具体的な例としては、以下のようなものがあります。
- 数の概念(量、大小、順序)が理解しにくい。
- 位取り(一の位、十の位など)の理解が難しい。
- 繰り上がりや繰り下がりの計算が難しい。
- 九九や簡単な計算式を覚えるのに時間がかかる。
- 計算のプロセスや手順を追うのが難しい。
- 図形やグラフの意味が理解しにくい。
- 文章問題から必要な情報を見つけ出し、計算式を立てるのが難しい。
- 論理的な思考や推論が苦手。
LDは、適切な指導法やサポートによって学習の困難を軽減できる可能性があります。一人ひとりの困難さに合わせた個別指導が有効です。
その他の発達障害
主要なASD、ADHD、LD以外にも、発達性協調運動症やチック症・トゥレット症候群なども発達障害の範疇に含まれることがあります。
チック症・トゥレット症候群
チック症は、突発的で、目的がなく、不随意な運動や音声の繰り返し(チック)が特徴です。運動チック(まばたき、首振り、肩すくめなど)や音声チック(咳払い、鼻すすり、単語の繰り返しなど)があります。トゥレット症候群は、複数の運動チックと1つ以上の音声チックが1年以上続く場合を指します。ストレスや緊張で悪化しやすい傾向がありますが、睡眠中には現れにくいとされます。
協調運動症
発達性協調運動症は、年齢や知的な発達に見合わない不器用さ(運動能力の遅れ)が特徴です。歩く、走る、跳ぶといった全身を使った粗大運動や、箸を使う、ボタンをかける、絵を描くといった手先の微細運動に困難が見られます。これにより、体育の授業についていけない、日常的な動作に時間がかかるといった困りごとが生じることがあります。
発達障害の全体的な特徴・共通する特性
ASD、ADHD、LDといった診断名に関わらず、発達障害を持つ人には共通して見られることのある特性がいくつかあります。これらの特性が複合的に影響し合い、日常生活での困難につながることがあります。
感覚過敏・感覚鈍麻
特定の感覚(視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚、固有受容覚、前庭覚)に対して、一般よりも過敏すぎたり(感覚過敏)、逆に鈍感すぎたり(感覚鈍感)する特性です。
- 感覚過敏:
- 特定の音が耳障りで耐えられない(掃除機の音、黒板をひっかく音など)。
- 蛍光灯の光や強い日差しがまぶしく感じる。
- 特定の匂いが苦手で気分が悪くなる。
- 服のタグや特定の素材の肌触りが不快で着られない。
- 人混みや騒がしい場所が苦手で疲れる。
- 感覚鈍感:
- 痛みや温度に気づきにくい。
- 空腹や満腹を感じにくい。
- 大きな音や強い光に気づきにくい。
- 体が触れていることに気づきにくい。
- じっとしていられず、常に体を動かしたり、壁にぶつかったりする。
感覚特性による困りごとは、本人のストレスや二次障害につながることもあります。イヤーマフを使用したり、触り心地の良い服を選んだりするなど、環境調整や工夫が有効です。
実行機能の偏り(計画・整理・時間管理の苦手さ)
実行機能とは、目標を設定し、計画を立て、実行し、結果を評価・修正するといった一連の認知能力のことです。発達障害を持つ人の中には、この実行機能に偏りがあり、特に計画性や整理整頓、時間管理などが苦手な傾向が見られることがあります。これはADHDの不注意の特性とも関連が深いです。
- やるべきことの優先順位をつけられない。
- 目標達成のために、具体的なステップを考えられない。
- 計画通りに物事を進めるのが難しい。
- 締め切りがあっても、ギリギリまで着手できない、または間に合わない。
- 複数の作業を同時にこなす(マルチタスク)のが苦手。
- 持ち物や書類の整理ができず、必要なものがすぐに見つからない。
- 時間の感覚が掴みにくく、待ち合わせに遅刻したり、作業に時間をかけすぎたりする。
これらの困難さは、仕事や学業、日常生活の様々な場面で支障をきたす可能性があります。タスク管理ツールの活用や、 ToDoリストの作成、タイマーの活用などが有効な対策となります。
情緒的な不安定さ
発達障害の特性を持つ人は、感情のコントロールが難しかったり、些細なことで強いストレスを感じたりして、情緒的に不安定になりやすいことがあります。これは、特性による生きづらさや、コミュニケーションのすれ違い、感覚過敏など様々な要因が影響しています。
- 感情の起伏が激しい、または感情表現が乏しい。
- 些細なことでカッとなったり、パニックになったりする。
- 不安や緊張を感じやすい。
- ストレスを溜め込みやすく、体調を崩しやすい。
- 気分の切り替えが難しい。
- 完璧主義で、思い通りにならないとひどく落ち込む。
感情の調整やストレス対処が苦手な場合、二次障害として不安障害やうつ病などを発症するリスクが高まります。リラックス法を身につけたり、信頼できる人に相談したり、専門家のアドバイスを受けたりすることが重要です。
発達障害の特徴【年齢別】
発達障害の特性は、年齢によって現れ方やそれに伴う困りごとが変化することがあります。成長段階に応じた理解と支援が求められます。
乳幼児期・子供の発達障害の特徴
乳幼児期や子供の時期は、発達の節目で特性が気づかれやすい時期です。言葉の発達の遅れや、遊び方、人との関わり方などに特徴が見られることがあります。
- 乳幼児期:
- 目が合いにくい、視線を合わせようとしない。
- 後追いや人見知りが少ない。
- 名前を呼んでも振り向かない。
- 指差しをしない、要求を言葉で伝えにくい。
- 特定の遊びや物にこだわり、他のことに興味を示さない。
- 抱っこを嫌がる、または特定の触り心地にこだわる。
- 極端な偏食がある。
- 睡眠や食事のリズムが不規則。
- 幼児期・学童期:
- 言葉の発達が遅れている、または一方的に話し続ける。
- 他の子供との遊び方が分からない、輪に入れない。
- ごっこ遊びやルールのある遊びが苦手。
- 友達への共感や気持ちの理解が難しい。
- 多動性や衝動性が強く、落ち着きがない。
- 順番を待てない、衝動的な行動が多い。
- 特定の音や感触に敏感で、パニックになることがある。
- 集団行動のルールを守るのが難しい。
- 読み書きや計算など、特定の学習につまずきが見られる(LD)。
- 不器用で、運動や手先を使った作業が苦手(協調運動症)。
この時期に特性に気づき、早期に適切な支援を受けることで、その後の成長や社会生活に良い影響を与えることが期待できます。
思春期の発達障害の特徴
思春期は、自己意識が高まり、人間関係が複雑化する時期です。子供の頃には目立たなかった特性が、この時期に顕在化し、困難が増すことがあります。
- 友人関係の構築や維持が難しくなる。
- クラスや部活など、集団内での立ち振る舞いが分からず孤立しやすい。
- 異性との関わり方に悩む。
- コミュニケーションのすれ違いから、いじめやトラブルに巻き込まれるリスク。
- 将来のこと(進路、就職など)を具体的に考えるのが難しく、不安を感じやすい。
- 成績が伸び悩む、特定の科目が極端に苦手。
- 反抗的な態度や衝動的な行動が増える。
- 自分の特性を認識し、自己肯定感が低下する。
- 不安障害やうつ病、摂食障害などの二次障害を発症しやすい。
思春期の発達障害への支援は、本人の自己理解を促し、ストレスマネジメントの方法を身につけること、そして安心して相談できる環境を整えることが重要です。
大人の発達障害の特徴
大人の発達障害は、幼少期から特性は持っていたものの、社会人になって仕事や対人関係、家庭生活などで困難を感じ、初めて診断に至るケースが増えています。子供の頃は周囲のサポートや環境によって特性がカバーされていたり、本人が強い努力で乗り越えてきたりした結果、大人になってから限界を迎えることがあります。
大人ASDのコミュニケーション・対人関係の特徴
- 職場での報連相(報告・連絡・相談)がスムーズにできない。
- 上司や同僚の指示の意図が読み取れない。
- 会議中に発言するタイミングが分からない、または場違いな発言をしてしまう。
- 職場の雑談や飲み会など、プライベートなコミュニケーションに馴染めない。
- 言葉を額面通りに受け取ってしまい、誤解が生じやすい。
- 相手の表情や声のトーンから感情を読み取るのが苦手。
- 冗談や社交辞令が理解できない。
- 特定の人物との人間関係でトラブルを繰り返しやすい。
大人ADHDの不注意・衝動性の特徴
- 仕事で期日管理ができず、納期遅れや締め切り破りが多い。
- ケアレスミスが多く、仕事の正確性に欠ける。
- 書類や持ち物の整理ができず、必要なものがすぐに見つからない。
- 会議やデスクワーク中に集中力が続かず、効率が悪い。
- 衝動買いをしてしまい、金銭管理が苦手。
- 後先考えずに発言したり行動したりして、人間関係や仕事でトラブルになる。
- 気分にムラがあり、計画通りに物事を進められない。
- 忘れ物や約束を忘れることが多い。
- 転職を繰り返しやすい。
大人の発達障害【仕事編】よくある困りごと
| 困りごと | 考えられる特性の例 |
|---|---|
| 指示を理解するのが難しい | ASD(言葉を字義通りに捉える)、ADHD(不注意で聞き漏らす) |
| 複数の業務を同時にこなせない(マルチタスク) | ADHD(集中力の切り替えが苦手)、実行機能の偏り |
| 優先順位をつけるのが苦手 | ADHD(注意の転導性)、実行機能の偏り |
| 整理整頓ができず、物をなくしやすい | ADHD(不注意、片付けが苦手)、実行機能の偏り |
| 時間管理が苦手で、遅刻や納期遅れが多い | ADHD(時間の感覚が掴みにくい)、実行機能の偏り |
| 報連相がうまくできない | ASD(コミュニケーションの困難)、ADHD(計画性がない、衝動的に話す) |
| 職場の人間関係に馴染めない | ASD(対人関係・コミュニケーションの困難、場の空気が読めない)、感覚過敏(騒がしい場所が苦手) |
| ストレス耐性が低い | 情緒的な不安定さ、感覚過敏、特性による生きづらさ |
| ミスが多い | ADHD(不注意、衝動性)、LD(読み書き・計算の困難) |
大人の発達障害【恋愛・結婚編】よくある困りごと
| 困りごと | 考えられる特性の例 |
|---|---|
| パートナーの気持ちを理解するのが難しい | ASD(相手の感情や意図の読み取りが苦手、共感が難しい) |
| 家事分担や生活習慣のルール調整が難しい | ASD(変化を嫌う、自分のやり方にこだわる)、実行機能の偏り(計画性) |
| 金銭管理が苦手(衝動買いなど) | ADHD(衝動性、計画性がない) |
| 衝動的な言動でパートナーを傷つけてしまう | ADHD(衝動性)、情緒的な不安定さ |
| 特定の趣味や物事に没頭しすぎてパートナーをおろそか | ASD(限定された興味・こだわり、過集中) |
| 記念日や約束事を忘れる | ADHD(不注意、忘れ物が多い) |
これらの困りごとは、特性によるものだと理解することで、本人やパートナーができる工夫や、必要な支援を見つけることにつながります。
発達障害の特徴【男女別】
発達障害の特性の現れ方は、男女によって異なる傾向があることが指摘されています。これは、生物学的な違いだけでなく、社会的な期待や性別役割の違いも影響していると考えられます。
女性の発達障害の特徴(定型発達を装う傾向など)
女性の場合、対人関係やコミュニケーションの困難さ、衝動性などの特性が男性ほど目立たないことがあります。その代わりに、「カモフラージュ」や「擬態」と呼ばれる、周囲の行動を模倣したり、マニュアル的に対応したりして、自分の特性を隠そうとする傾向が強いと言われています。
- カモフラージュ・擬態:
- 定型発達の人の会話や振る舞いを観察し、真似ることでその場に適応しようとする。
- マニュアルやルールを徹底的に覚え、それに従って行動することでミスを防ごうとする。
- 無理に合わせて「普通」を装うことで、内面に大きなストレスや疲労を溜め込む。
- 特性の現れ方:
- ADHDの場合、不注意優勢型が多く、多動性や衝動性があまり目立たないことがある(忘れ物が多い、片付けられない、期日管理が苦手など)。
- ASDの場合、表面的なコミュニケーションはできても、深い関係を築くのが苦手だったり、特定のことへの強いこだわりが内面で密かに続けられたりする。
- 感覚過敏が強く、特定の音や匂いに耐えられないといった困りごとがある。
- 情緒的に不安定になりやすく、不安障害や摂食障害などの二次障害を併発しやすい。
女性は特性が外から見えにくいため、困りごとを抱えていても周囲に理解されにくく、診断に至るのが遅れる傾向があると言われています。長年の生きづらさや、二次障害で医療機関を受診した際に、初めて発達障害の特性に気づくというケースも少なくありません。
発達障害のグレーゾーンとは?特徴や診断との違い
「グレーゾーン」という言葉は、医学的な診断名ではありません。一般的に、発達障害の診断基準は満たさないものの、発達障害の特性が一部見られたり、特性による困難さを抱えていたりする状態を指して使われます。
グレーゾーンの人も、診断のある人と同様に、コミュニケーションや対人関係、集中力、衝動性、感覚、学習などに偏りによる困りごとを感じていることがあります。例えば、「少し落ち着きがない」「忘れっぽいところがある」「場の空気を読むのが苦手な時がある」といった、日常で「ちょっと気になるな」と感じる程度の特性が見られることがあります。
診断との一番の違いは、診断基準を満たすか、満たさないかという点です。診断は、国際的な基準(DSM-5など)に基づいて、医師が総合的に判断して行います。グレーゾーンは、この診断基準を明確には満たさない状態です。
しかし、診断がないからといって困りごとがないわけではありません。グレーゾーンの人も、特性による生きづらさを感じたり、学校や仕事で困難を抱えたりすることがあります。重要なのは、診断の有無にかかわらず、本人がどのような特性を持ち、どのようなことで困っているのかを理解し、その困りごとに対して適切な工夫や支援を見つけることです。診断がなくても、専門機関に相談したり、自分に合った対処法を身につけたりすることは可能です。
発達障害の診断について
発達障害の診断は、専門の医師(主に精神科医や心療内科医、児童精神科医)によって行われます。診断は、問診や生育歴の確認、心理検査、行動観察などを通して、総合的に判断されます。
診断基準(DSM-5など)
発達障害の診断には、世界保健機関(WHO)の「疾病及び関連保健問題の国際統計分類(ICD)」や、アメリカ精神医学会(APA)の「精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM)」といった国際的な診断基準が用いられます。現在、広く使われているのはDSM-5(または改訂版のDSM-5-TR)です。
これらの診断基準には、各発達障害の特性に関する具体的な項目が列挙されており、一定数以上の項目に該当することや、特性によって日常生活や社会生活に支障が出ていることなどが診断の要件とされています。ただし、診断は単にチェックリストに当てはめるだけでなく、医師が様々な情報を統合して慎重に行います。
発達障害の診断の流れ
発達障害の診断を受ける場合の一般的な流れは以下のようになります。
- 相談先の検討・予約: 発達障害の診断や相談が可能な医療機関(精神科、心療内科、児童精神科など)や専門機関(発達障害者支援センターなど)を探し、予約を取ります。初診の予約が取りにくい場合もあります。
- 問診・情報収集: 医師や心理士が、本人や家族から生育歴、これまでの発達の様子、現在の困りごと、既往歴、家族歴などについて詳しく聞き取りを行います。可能であれば、母子手帳や学校の通知表など、幼少期の様子がわかる資料があると役立つことがあります。
- 心理検査: 知能検査(WAIS-IV, WISC-Vなど)や、ASD・ADHDの特性を評価する質問紙やスケール(AQ, EQ, CAARS, AD/HD RSなど)など、いくつかの心理検査が行われます。これらの検査は、特性の傾向や認知の偏りを客観的に把握するために役立ちます。
- 行動観察: 診察や検査中の本人の様子、人との関わり方などを観察します。子供の場合は、遊びの様子などが観察されることもあります。
- 医師による診断: 問診、情報収集、心理検査の結果、行動観察などを総合的に判断し、医師が診断を下します。診断結果や特性について説明を受け、今後の対応や支援について話し合います。
- 診断後のフォロー: 必要に応じて、治療(薬物療法など)、カウンセリング、ペアレントトレーニング、SST(ソーシャルスキルトレーニング)などの支援やプログラムが提案されます。
診断までの期間は、医療機関によって異なりますが、初診から診断確定まで数ヶ月かかることも珍しくありません。
診断を受けるメリット・デメリット
発達障害の診断を受けることには、以下のようなメリットとデメリットが考えられます。診断を受けるかどうかは、ご自身の状況や考え方によって慎重に判断することが大切です。
メリット
- 特性の理解が進む: 自分の困りごとが発達障害の特性によるものだと明確になることで、自己理解が進み、漠然とした不安が解消されることがあります。
- 適切な支援やサービスにつながりやすい: 診断があることで、障害者手帳の取得、障害福祉サービス(障害者雇用、就労移行支援、自立訓練など)、各種助成金、学校での合理的配慮など、利用できる支援やサービスが広がる場合があります。
- 周囲の理解を得やすくなる可能性がある: 診断名を伝えることで、家族、友人、職場の同僚などに特性を理解してもらいやすくなり、配慮やサポートを得やすくなることがあります。
- 医学的なアプローチ(薬物療法など)が選択肢に入る: ADHDなどでは、症状緩和のために薬物療法が有効な場合があります。診断があれば、そうした治療の選択肢も検討できます。
デメリット
- 診断名へのショック: 想定していたとはいえ、診断名を聞いてショックを受けたり、落ち込んだりすることがあります。
- 費用がかかる: 診断に必要な検査や診察には費用がかかります。保険が適用される場合もありますが、一部保険適用外の検査や自由診療となることもあります。
- 社会的な偏見のリスク: 発達障害に対する理解は進んできていますが、残念ながらまだ偏見が存在する場合があります。診断名を知られることによる差別や誤解のリスクがゼロではありません。
- 職場で伝えるかどうかの判断が必要: 診断名を職場に伝えるか、どのように伝えるかなど、難しい判断が必要になる場合があります。伝えることで不利益を被る可能性も考慮する必要があります。
診断を受けるかどうかは、メリット・デメリットを十分に比較検討し、信頼できる専門家や相談機関と話し合った上で決定することをおすすめします。
発達障害かも?と思ったら【相談先・支援】
「もしかしたら自分や子供は発達障害の特性があるかもしれない」「日常生活で困りごとが多くて辛い」と感じたら、一人で抱え込まずに専門機関に相談することが大切です。自己判断はせず、専門家の意見を聞くことから始めてみましょう。
主な相談先や支援機関は以下の通りです。
医療機関(精神科・心療内科)
発達障害の診断や治療を行う専門医がいます。精神科、心療内科、児童精神科などがこれにあたります。
- 役割: 診断、特性に関する医学的な説明、二次障害(不安障害、うつ病など)の治療、薬物療法(ADHDなど)、カウンセリングなど。
- 探し方: インターネットで「(地域名) 精神科 発達障害 診断」などで検索するか、後述の発達障害者支援センターに相談して紹介を受ける方法があります。発達障害の診療を行っているか、事前に確認することをおすすめします。
発達障害者支援センター
各都道府県および指定都市に設置されている公的な相談支援機関です。本人や家族、関係機関からの様々な相談に応じてくれます。
- 役割: 発達障害に関する相談・情報提供、発達に関するアセスメント、専門機関の紹介、ペアレントトレーニング、普及啓発活動など。
- 特徴: 診断の有無にかかわらず相談できます。どのような支援があるかを知りたい場合に頼りになります。
- 探し方: 厚生労働省や各自治体のウェブサイトで検索できます。
就労移行支援事業所など
大人で就職や転職、働き続けることに困難を感じている場合、就労に関する支援機関があります。
- 就労移行支援事業所: 障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業所です。一般企業等への就労を目指す障害のある方に対し、就労に必要な知識・能力向上のための訓練、求職活動の支援、職場定着のための支援を行います。
- ハローワーク(専門窓口): 障害のある方向けの専門窓口があり、就職相談や求人紹介、各種支援制度の情報提供などを行っています。
- 地域障害者職業センター: 障害のある方に対し、職業リハビリテーションの専門的なサービスを提供しています。
その他、地域の保健センター、子育て支援センター、学校のスクールカウンセラー、障害者相談支援事業所など、様々な相談先があります。まずは身近な相談しやすい窓口に連絡してみるのも良いでしょう。
発達障害に関するよくある質問(PAAより)
発達障害で一番多いのは?(ADHDについて)
発達障害の正確な統計データは取得が難しく、研究によって数値に幅がありますが、児童を対象とした調査では、注意欠如・多動症(ADHD)や限局性学習症(LD)が比較的多い傾向にあると言われています。ただし、複数の特性が併存していることも多いため、「一番多い」と断定することは難しい側面もあります。大人の診断数については、近年ASDやADHDで診断される人が増えています。
大人発達障害グレーゾーンの特徴は?
大人で発達障害のグレーゾーンと呼ばれる人の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。
- 診断基準は満たさないが、不注意や衝動性、コミュニケーションの困難さなど、発達障害の特性に似た傾向がある。
- 子供の頃から忘れ物が多い、片付けが苦手、集団に馴染みにくいといった困りごとがあったが、診断には至らなかった。
- 知的な遅れはないが、仕事や学業、日常生活で特定の困りごと(期日管理が苦手、人間関係でつまずきやすい、ストレスを溜めやすいなど)を抱えている。
- 「ちょっと変わった人」「不器用な人」などと見られることがある。
- 困りごとを「自分の努力不足」だと感じてしまい、自己肯定感が低くなりがち。
- 二次障害として、うつ病や不安障害を発症することがある。
グレーゾーンの場合でも、特性を理解し、自分に合った工夫や環境調整、必要に応じて専門家のサポートを受けることで、困りごとを軽減することが可能です。
発達障害の大人の喋り方の特徴は?(ASDの話し方など)
発達障害のある大人の喋り方には、特性によって様々な傾向が見られることがあります。ただし、個人差が非常に大きく、全ての人が当てはまるわけではありません。
- ASDの傾向:
- 単調で抑揚があまりない話し方。
- 声の大きさが適切でない(大きすぎる、小さすぎる)。
- 一方的に話し続け、相手の反応に気づきにくい。
- 言葉を字義通りに使い、比喩や曖昧な表現が苦手。
- 早口になったり、逆に言葉が出てくるのに時間がかかったりする。
- 専門用語や難しい言葉を好んで使う。
- 視線が合わない、または合すぎる。
- ADHDの傾向:
- 早口で畳み掛けるように話す。
- 話があちこちに飛んでしまい、まとまりがない。
- 人の話を遮って、思いついたことをすぐに口にしてしまう(衝動性)。
- じっとしていられず、話しながら体を動かしたり、そわそわしたりする。
- 必要な情報を伝え忘れやすい(不注意)。
これらの話し方の特徴が、コミュニケーションのすれ違いや誤解につながることもあります。自分の話し方の傾向を理解し、ゆっくり話す、話す前に一度立ち止まって考える、伝えたいことをメモにまとめるなどの工夫が役立つことがあります。
発達障害の人は何が苦手ですか?
発達障害のある人が苦手とすることは、特性の種類や個人によって大きく異なります。しかし、共通して見られる傾向としては、以下のようなものが挙げられます。
- コミュニケーション:
- 相手の意図を読み取る、気持ちを察する、冗談や皮肉を理解する、適切なタイミングで会話に参加するといった、非言語的・社会的なコミュニケーション。
- 対人関係: 人との適切な距離感を保つ、集団の中で立ち振る舞う、友人関係や恋愛関係を円滑に進めることなど。
- 変化への対応: 予期せぬ出来事や予定変更、新しい環境への適応。
- 感覚刺激の調整: 特定の音、光、匂い、触覚などに対する過敏さや鈍感さによる困難。
- 計画・整理・時間管理: 目標設定、計画立案、実行、優先順位付け、時間管理、整理整頓といった実行機能に関わること。
- 特定の学習: 読み書き、計算、推論など、特定の学習領域。
一方で、発達障害のある人は、特定の物事への強い関心や集中力、ユニークな発想力、優れた記憶力など、得意なことや強みを持っていることも多くあります。苦手なことだけでなく、得意なことにも目を向け、それを活かす方法を見つけることが大切です。
まとめ:発達障害の特性理解と前向きな対処へ
発達障害は、生まれつきの脳機能の偏りによる多様な特性であり、決して病気や努力不足によるものではありません。自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症(LD)など、様々な種類があり、特性の現れ方や困りごとは一人ひとり異なります。年齢や性別によっても、特性の表出やそれに伴う生きづらさが変化することがあります。
もし、ご自身や周囲の人に発達障害の特性に似た傾向があり、日常生活や社会生活で困難を感じている場合は、一人で悩まずに専門機関に相談してみることをおすすめします。診断を受けるかどうかは個人の選択ですが、専門家の意見を聞くことは、特性を理解し、自分に合った対処法や環境調整を見つけるための第一歩となります。
特性をネガティブなものとして捉えるだけでなく、自分の個性として理解し、困りごとに対して適切な工夫や支援を活用することで、より快適に自分らしく生きていくことは十分に可能です。特性との付き合い方を知り、前向きに対処していくことで、人生をより豊かなものにしていけるでしょう。
【免責事項】
この記事は、発達障害に関する一般的な情報提供を目的としており、医学的な診断や治療を保証するものではありません。個別の症状や状況については、必ず専門の医療機関にご相談ください。この記事の情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いません。