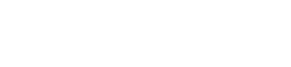病気や心身の不調によって仕事を続けることが困難になった場合、休職という選択肢があります。休職するためには、会社に診断書の提出を求められることが一般的です。この診断書は、単に病気であることを証明するだけでなく、休職期間や必要な配慮など、休職中の重要な取り決めに関わる役割を果たします。
本記事では、休職に必要な診断書のもらい方から、会社への提出方法、診断書に記載される内容、期間、費用、そして休職中の過ごし方や復帰に向けた準備まで、休職診断書に関するあらゆる情報を詳しく解説します。特に、メンタルヘルスの不調による休職を考えている方に向けて、精神科や心療内科での診断書のもらい方についても触れています。休職を検討している方、または休職診断書について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
休職に診断書は必要?
体調を崩し、医師から一定期間の療養が必要と診断された場合、会社を休職することがあります。多くの会社では、休職を申請する際に医師の診断書の提出を義務付けています。診断書は、病気や怪我によって就業が困難である状態を医学的に証明する書類であり、休職制度を利用するための重要な根拠となります。
診断書の役割とは
- 医学的な証明: 労働者が病気や怪我によって現在の業務を遂行することが困難である、または休養が必要であることを、医師という専門家が医学的見地から証明します。これにより、休職の正当性が会社に示されます。
- 休職の必要性の明示: 診断書には、病名や病状だけでなく、「〇ヶ月程度の休養が必要」「就労不可」といった、休職が必要な理由や状態が具体的に記載されます。
- 休職期間の目安: 多くの診断書には、必要な休養期間が記載されます。これはあくまで医師の見立てですが、会社が休職期間を決定する上での重要な参考となります。
- 会社への配慮依頼: 病状によっては、復帰に向けての段階的な就労(リハビリ出勤など)や、業務内容、勤務時間の調整など、会社に求めるべき配慮事項が記載されることがあります。これにより、会社側は適切なサポート体制を検討しやすくなります。
- 傷病手当金申請の根拠: 健康保険から支給される傷病手当金を申請する際に、診断書は病気や怪我による療養が必要であることを証明する重要な書類となります。
このように、診断書は休職を円滑に進めるために、会社と労働者双方にとって欠かせない役割を担っています。
診断書がないと休職できない?
法律上、労働基準法などで会社が従業員の休職申請に対して診断書の提出を義務付ける、という明確な規定はありません。しかし、多くの企業では就業規則に休職に関する規定を設けており、その中で休職申請の条件として医師の診断書の提出を義務付けているのが一般的です。
これは、会社が従業員の健康状態を把握し、適切な休職期間や復職支援を判断するために診断書が必要だからです。診断書がない場合、会社側は病状の程度や休養の必要性を正確に判断することが難しくなり、休職申請が認められない可能性があります。
もし、会社の就業規則に「休職には医師の診断書の提出が必要である」と明記されている場合は、原則として診断書なしでの休職は認められません。まずは会社の就業規則を確認し、不明な点があれば人事担当者や上司に相談してみましょう。
ただし、緊急性が高い場合や、診断書の取得に時間がかかる特殊な事情がある場合は、一時的に診断書なしで休みに入り、後日提出を求められるケースもあります。この場合も、必ず事前に会社に相談し、指示を仰ぐようにしてください。無断で欠勤が続くと、休職ではなく欠勤扱いとなり、最悪の場合、懲戒処分の対象となる可能性もあります。
結論として、多くの会社では休職に診断書が必須であり、円滑な手続きのためにも診断書を用意することが強く推奨されます。
休職診断書のもらい方
休職診断書を取得するためには、まず医療機関を受診し、医師の診察を受ける必要があります。病気や怪我の状態、就業への影響などを医師に正確に伝え、休養が必要であると判断された場合に診断書を発行してもらえます。
診断書発行までの流れ
診断書を発行してもらうための一般的な流れは以下の通りです。
- 医療機関の受診: 体調不良を感じたら、まずは適切な診療科(内科、整形外科、精神科など)のある医療機関を受診します。会社を休む必要があると感じるほど体調が悪い場合は、早めに受診することが重要です。
- 医師への相談: 診察時に、現在の症状、それが仕事にどのように影響しているか、仕事を続けるのがどれほど困難かなどを具体的に医師に伝えます。「休職を検討しており、会社に提出するための診断書が必要なのですが、書いていただけますか?」と正直に相談しましょう。
- 病状の診察と判断: 医師はあなたの病状を診察し、問診の内容と合わせて、医学的な見地から休職が必要かどうかを判断します。この際、現在の業務内容や労働環境についても伝えられると、医師がより適切な判断をしやすくなります。
- 診断書の発行依頼: 医師が休職の必要性を認めた場合、診断書の発行を依頼します。診断書には、氏名、生年月日、病名、現在の病状、就労への影響、必要な休養期間などが記載されます。会社によっては、診断書に記載してほしい項目(例:具体的な業務制限、復帰に向けた配慮事項など)がある場合があるため、事前に会社に確認しておくとスムーズです。
- 診断書の受け取りと費用支払い: 診断書は即日発行されることもありますが、医師が作成する時間が必要な場合や、特別な記載が必要な場合は数日かかることもあります。発行された診断書を受け取り、窓口で費用を支払います。費用は医療機関によって異なります(後述)。
診断書の発行には、症状が医学的に証明され、就業が困難であると医師が判断することが前提となります。医師の診察なしに診断書だけを発行してもらうことはできません。
精神科・心療内科でのもらい方(メンタル不調の場合)
うつ病や適応障害、不安障害などのメンタルヘルスの不調により休職する場合、精神科または心療内科を受診することになります。これらの診療科で診断書をもらう場合も基本的な流れは同じですが、いくつかのポイントがあります。
- 医療機関の選択: 精神科と心療内科は似ていますが、精神科は精神疾患全般を扱い、心療内科は心身症(ストレスが原因で身体的な症状が現れる病気)を中心に扱います。どちらを受診するか迷う場合は、症状に合わせて選びますが、どちらでも休職診断書の発行は可能です。職場の近くや通いやすい場所にあるか、予約が必要かなどを事前に確認しましょう。
- 初診時の伝え方: 初診時は、現在の精神的な症状(ゆううつな気分、意欲の低下、不眠、不安感など)、それが仕事のパフォーマンスや日常生活にどのように影響しているか(集中できない、ミスが増えた、朝起きられないなど)を具体的に医師に伝えましょう。抱えている悩みや、休職を検討していること、診断書が必要であることを正直に相談することが重要です。
- 診断書作成までの期間: 精神疾患の場合、一度の診察ですぐに診断名が確定し、休職が必要かどうかの判断ができるとは限りません。複数回の診察や、心理検査などを経て診断が確定し、その上で休職の必要性が判断されることがあります。そのため、診断書の発行までに時間がかかる可能性があることを理解しておきましょう。会社に急ぎで提出する必要がある場合は、その旨を医師に伝え、いつ頃発行可能か確認しておくと良いでしょう。
- 診断書の記載内容: メンタルヘルスの診断書には、病名(例:うつ病、適応障害など)、症状の詳細、就労可否(例:現在の業務遂行は困難、〇ヶ月の休養が必要)、具体的な業務制限(例:残業不可、出張不可、対人業務を控えるなど)、復職に向けた指示(例:段階的な就労が望ましい)などが記載されることがあります。会社とのコミュニケーションのために、これらの内容について医師とよく話し合うことが大切です。
メンタルヘルスの不調は、見た目には分かりにくいため、症状を具体的に伝えることが医師の適切な判断につながります。また、休職は治療の一環として非常に有効な場合がありますので、医師と相談しながら慎重に進めていきましょう。
診断書をあとから書いてもらうことは可能?
体調が非常に悪く、すぐにでも仕事を休む必要がある場合、診断書を取得する前に会社に連絡して休み始めることがあります。このようなケースで、後から医師に休職期間開始日に遡って診断書を書いてもらうことは可能なのでしょうか。
結論から言うと、遡って診断書を発行してもらうことは、医師が患者の病状を客観的に判断できる場合に限り可能です。
医師は、診察した時点での患者の病状に基づいて診断書を作成するのが原則です。しかし、患者が体調不良で受診できず、後日受診した場合でも、以下のような状況であれば遡って記載してもらえる可能性があります。
- 症状が継続している場合: 受診できなかった期間も、診断書発行を依頼している時点と同じような症状が継続しており、医師が問診や診察によってその状況を把握・推測できる場合。
- 過去の受診記録がある場合: 遡りたい期間の直前に同じ症状で受診しており、その際に医師がすでに病状を把握していた場合。
- 明確な原因がある場合: 診断書の開始日に遡って病状が悪化した明確な原因があり、医師がそれを医学的に妥当と判断できる場合(例:特定の出来事をきっかけにうつ病が悪化し、一時的に受診できなかったなど)。
ただし、これらの場合でも、医師は自身の医学的な判断に基づいて診断書を作成するため、必ずしも希望通りに遡って記載されるとは限りません。また、医師によっては一切遡っての記載に応じない方針の場合もあります。
やむを得ず事後的に診断書の発行を依頼する場合は、正直に医師に状況を説明し、相談してみましょう。可能な限り、体調不良を感じたら速やかに受診し、その場で診断書の発行を依頼するのが最もスムーズな方法です。
医師が診断書を書かないケース
医師は、医学的な根拠に基づき、患者の病状を客観的に診断して診断書を作成します。そのため、患者が診断書を求めても、医師が発行しない、あるいは希望する内容で書かないケースも存在します。
医師が診断書を書かない、または希望する内容で書かない主なケースは以下の通りです。
- 医学的な休職の必要性が認められない: 患者が休職を希望していても、医師が診察の結果、現在の病状が就業を困難とするほどではない、あるいは医学的に休養が必要な状態ではないと判断した場合です。医師は、あくまで医学的な見地から判断するため、患者の主観的な「休みたい」という希望だけでは診断書は発行されません。
- 病状が軽微である: 軽い風邪や一時的な疲労など、数日の休養で回復が見込めるような病状の場合、医師は休職ではなく数日間の欠勤を推奨することがあります。休職は一般的に1ヶ月以上の長期にわたる療養が必要な場合に適用されることが多いためです。
- 診断書を悪用する可能性があると疑われる: 過去に虚偽の申告で診断書を取得しようとした経緯がある、あるいは診察時の言動から診断書を不正に利用する可能性があると医師が判断した場合、発行を拒否することがあります。
- 希望する内容と医学的事実が異なる: 患者が診断書に特定の病名や期間の記載を強く希望しても、医師の診察結果や医学的な根拠と異なる場合は、その通りの内容で書くことはできません。医師は医療倫理に基づいて診断書を作成します。
- 専門外の疾患: 専門外の疾患について診断書の作成を求められた場合、正確な診断や判断ができないため、専門医への受診を促し、診断書の発行を断ることがあります。
医師が診断書を発行しない場合は、その理由を丁寧に説明してくれるはずです。医師の判断を尊重し、必要であれば別の医療機関を受診するなど、今後の対応について相談しましょう。
休職診断書の記載内容と確認すべきポイント
休職診断書には、休職の根拠となる重要な情報が記載されています。会社に提出する前に、診断書の内容をしっかりと確認することが大切です。特に、会社が休職を判断し、必要な手続きを進める上で確認が必要な項目があります。
診断書に記載される主な項目
一般的な休職診断書には、以下の項目が記載されています。様式は医療機関や診断書の種類(診断書、就労不能証明書など)によって多少異なります。
- 氏名、生年月日: 患者本人の氏名と生年月日が記載されます。
- 傷病名: 現在の病気や怪我の正式な診断名が記載されます(例:うつ病、適応障害、腰部椎間板ヘルニアなど)。
- 現在の病状: 病気や怪我の状態、具体的な症状について記載されます。精神疾患の場合は、不眠、意欲低下、集中力低下などが、身体疾患の場合は痛みや機能制限などが記載されます。
- 経過: 発症からの簡単な経緯や、これまでの治療状況について記載されることがあります。
- 治療内容: 現在行っている治療(投薬、リハビリテーション、精神療法など)について記載されることがあります。
- 就労への影響: 現在の病状が就業にどのように影響しているか、就労の可否や制限について記載されます。「就労不可」「〇ヶ月間の休養が必要」「軽作業なら可能」など、具体的な状態が示されます。
- 必要な休養期間(見込み): 医師が判断する、病状回復に必要な休養期間の目安が記載されます。これはあくまで「見込み」であり、病状の回復状況によって前後する可能性があります。
- その他会社への指示・意見: 復帰に向けた段階的な就労の提案(リハビリ出勤)、特定の業務からの除外、勤務時間の短縮など、会社が従業員に配慮すべき点や、復職に関する医師の意見が記載されることがあります。
- 診断年月日: 診断書を作成した日付が記載されます。
- 医療機関名、医師の氏名、捺印: 診断書を発行した医療機関の情報と、医師の氏名、資格を示す捺印がなされます。
これらの項目は、会社が休職を認めるかどうかの判断や、休職期間中の対応、復職支援計画の策定において重要な情報源となります。
会社に確認が必要な項目(期間など)
診断書の内容を確認する際に、特に会社との関係で重要なのが「休養期間」と「その他会社への指示・意見」の項目です。会社に提出する前に、これらの項目について会社の就業規則や人事担当者と確認しておくべき点があります。
- 休養期間の妥当性:
- 診断書に記載された休養期間が、会社の定める休職期間の上限を超えていないか確認しましょう。会社の就業規則には、休職できる最長期間が定められています。診断書の期間が上限を超える場合、会社との調整が必要になったり、休職ではなく退職扱いとなる可能性もあります。
- 診断書の期間が会社の定める休職期間の単位(例:1ヶ月単位、3ヶ月単位など)に合っているか確認します。会社によっては、診断書の期間に合わせて休職期間を区切る場合があります。
- 「〇ヶ月間の休養が必要」という記載はあくまで医師の見込みです。会社の規定によっては、まず一定期間(例:3ヶ月)休職し、期間満了前に再度診断書を提出して延長の可否を判断するという流れになることもあります。
- その他会社への指示・意見(特に復帰関連):
- 診断書に「復職には段階的な就労が望ましい」「特定の業務は避けるべき」といった会社への指示や意見が記載されている場合、会社がそれらの配慮に対応可能か、どのような形で実施されるのかを事前に確認しておくと、復職時のミスマッチを防ぐことができます。
- 特にメンタルヘルスの場合、どのような状況になれば復職可能かの目安(例:「安定した睡眠がとれる」「午前中から活動できる」「公共交通機関を利用して通勤できる」など)が医師の意見として記載されていると、会社も復職に向けた準備を進めやすくなります。会社側から、診断書に追記や修正を依頼されることもありますので、その場合は再度医師に相談しましょう。
これらの項目は、会社の制度や規定によって対応が異なるため、診断書を提出する前に必ず会社の就業規則を確認するか、人事担当者に相談して確認しておくことが重要です。
診断書の費用
診断書の発行にかかる費用は、医療機関の種類(病院、クリニック)、診療科、診断書の種類、そして健康保険が適用されるかどうかによって異なります。
費用相場:
- 一般的な休職診断書: 健康保険が適用されない自費診療となるのが一般的です。費用は医療機関によって幅がありますが、3,000円~10,000円程度が相場です。大規模な病院や専門性の高い診断書は高くなる傾向があります。
- 傷病手当金申請用の医師の意見書など: こちらも基本的には自費診療で、上記の相場と同様か、少し高くなることもあります。
- 保険適用となる場合: 業務上の病気や怪我(労働災害)の場合は、労災保険が適用され、診断書費用も労災保険から支払われることがあります。また、診断書の提出自体が治療の一環とみなされる場合(例えば、リワークプログラム参加のために医師の意見書が必要な場合など)、例外的に保険適用となる可能性もゼロではありませんが、非常に稀です。
確認すべき点:
- 事前に費用を確認する: 診断書が必要だと分かった時点で、受診する医療機関に診断書の発行費用について問い合わせておくと安心です。「休職用の診断書の発行費用はいくらですか?」と具体的に聞くと良いでしょう。
- 会社の規定を確認する: 会社によっては、休職診断書の費用の一部または全部を補助する制度がある場合もあります。念のため、会社の就業規則や規程を確認するか、人事担当者に問い合わせてみましょう。
診断書は健康保険の対象外となることが多いため、費用については自己負担となることを理解しておきましょう。
休職期間について
休職診断書には、医師が必要と判断する休養期間の見込みが記載されます。この期間は、会社が休職を認める期間を決定する上で重要な要素となりますが、会社の就業規則によって、休職期間の上限や運用方法は異なります。
診断書に記載される一般的な期間
休職診断書に記載される休養期間は、病状や治療経過によって異なりますが、一般的には以下のような期間が記載されることが多いです。
- 精神疾患(うつ病、適応障害など): 初回は1ヶ月~3ヶ月と記載されることが最も多いです。精神疾患の治療には一定の期間がかかるため、病状の回復を見ながら、必要に応じて休職期間が延長されるケースが多く見られます。初めての休職の場合、まず数ヶ月で様子を見る、という医師の判断が反映されやすいです。
- 身体疾患(怪我や手術後など): 疾患の種類や手術の規模、回復状況によって様々です。骨折や手術後のリハビリ期間を含めて1ヶ月~数ヶ月と記載されることもあれば、病状が安定するまでの期間として記載されることもあります。
診断書に記載される期間は、あくまで「見込み」です。この期間内に病状が回復するとは限りませんし、逆に早く回復して復職が可能になることもあります。重要なのは、この診断書の期間を参考に、会社が就業規則に基づいて正式な休職期間を決定するということです。会社の休職期間は、診断書の期間より短い場合も長い場合もありますが、多くの場合は診断書の期間を考慮して設定されます。
休職期間の延長・再診断書
診断書に記載された休職期間が満了しても病状が回復せず、引き続き療養が必要な場合は、休職期間の延長を申請することができます。この際、多くの会社では改めて医師の診断書の提出を求められます。
休職期間延長の流れ:
- 主治医に相談: 休職期間満了が近づいてきたら、主治医に現在の病状と今後の見通しについて相談します。引き続き休職が必要であると判断された場合は、その旨を伝えて再診断書の発行を依頼します。
- 再診断書の発行依頼: 主治医に、休職期間を延長するための再診断書(または診断書)の発行を依頼します。この診断書には、現在の病状、なぜさらに休養が必要なのか、どの程度の期間が必要か(見込み)などが記載されます。
- 会社への連絡と再診断書の提出: 休職期間満了日までに、会社の人事担当者や上司に、病状が回復しておらず休職期間の延長が必要であることを連絡します。その上で、主治医から発行された再診断書を提出します。提出期限は会社の規定によりますので、事前に確認しておきましょう。
- 会社の判断: 提出された再診断書に基づき、会社は就業規則に定められた休職期間の上限や、病状、今後の見通しなどを考慮して、休職期間の延長を認めるかどうかの判断を行います。
注意点:
- 会社の休職期間上限: 会社の就業規則には、通算または一回の休職期間に上限が定められているのが一般的です。この上限を超える期間の延長は認められません。上限に達した場合は、休職期間満了をもって退職となるのが通常です。
- 診断書の提出期限: 再診断書の提出期限を過ぎてしまうと、休職期間満了をもって自動的に復職または退職となる場合があります。必ず会社の規定を確認し、期日までに提出できるように早めに手続きを進めましょう。
- 病状の具体的な説明: 再診断書には、前回からの病状の変化や、回復のためにどのような療養が必要なのか、具体的な説明があると会社も判断しやすくなります。主治医とよく相談し、必要な情報を記載してもらいましょう。
休職期間の延長は、会社の制度に基づいて行われます。不明な点は、遠慮なく会社の会社の担当者に確認することが大切です。
休職期間が切れたらどうなる?
診断書に記載された期間や、会社の定める休職期間が満了した場合、原則として以下のいずれかの対応が取られます。
- 復職: 病状が回復し、元の部署や業務内容、あるいは医師が復職可能と判断する程度の業務であれば遂行できると認められた場合、復職となります。復職に際しては、後述する復職支援の手続きや面談が行われるのが一般的です。
- 休職期間の延長: 前述の通り、病状が回復していない場合は、再診断書の提出など会社の定める手続きを経て、休職期間が延長される可能性があります。ただし、会社の休職期間の上限に達していないことが条件です。
- 退職: 会社の定める休職期間の上限に達しても病状が回復せず、就業が困難な状態が続いている場合、休職期間満了をもって退職となります。これは会社の就業規則に基づいて行われます。「自然退職」として扱われることが多く、懲戒解雇などとは異なります。
重要なのは、休職期間が満了する前に、自身の病状と今後の見通しについて主治医とよく話し合い、会社側とも密にコミュニケーションを取ることです。
休職期間満了間際の対応:
- 主治医との相談: 休職期間満了日の1ヶ月~2ヶ月前になったら、必ず主治医に診察してもらい、現在の病状と、休職期間満了日時点で復職が可能か、それとも延長が必要か、あるいは就業自体が困難な状況かを判断してもらいます。
- 会社への報告: 主治医の判断に基づき、会社の人事担当者や上司に、休職期間満了後の意向(復職希望、延長希望、退職意向など)と病状を報告します。必要であれば、主治医から診断書や意見書を改めて発行してもらいます。
- 会社の復職面談など: 会社が復職可能と判断した場合、産業医や人事担当者との面談が実施されることがあります。病状や就業上の配慮について話し合います。
休職期間満了間際に病状が回復せず、休職期間延長も会社の規定で認められない場合は、残念ながら退職を選択せざるを得ない状況となります。そうならないためにも、休職期間中は治療に専念し、会社の制度を十分に理解しておくことが大切です。
診断書提出後の手続きと会社の対応
診断書を会社に提出した後、会社側は診断書の内容に基づき休職の判断や手続きを進めます。労働者側も、休職中の生活や今後の手続きについて理解しておく必要があります。
会社への診断書提出方法
休職診断書を会社に提出する方法は、会社の規定や規模によって異なりますが、一般的な流れは以下の通りです。
- 誰に提出するか: 通常は、直属の上司または人事部の担当者に提出します。会社の休職規定や、過去に休職したことのある同僚などに確認してみましょう。
- 提出のタイミング: 体調不良を感じ、医師の診断を受けた後、可能な限り速やかに会社に連絡し、休職を検討している旨を伝えます。その上で、診断書が手元に届き次第、できるだけ早く提出します。遅れる場合は、いつ頃提出できるか連絡することが重要です。
- 提出方法:
- 直接手渡し: 上司や人事担当者に直接手渡しするのが最も確実です。簡単な状況説明もできます。
- 郵送: 遠方の場合や、直接会うのが難しい場合は郵送します。特定記録郵便や簡易書留など、追跡可能な方法で送付すると安心です。送付前にコピーを取っておくことをお勧めします。
- メール・FAX: 会社の指示によっては、まずメールやFAXでスキャンした画像を提出し、後日原本を郵送または提出するという対応が認められる場合もあります。これは緊急の場合の対応であり、原則は原本の提出が求められます。
- 提出時の添え状: 診断書のみを提出するのではなく、簡単な添え状を添付すると丁寧です。添え状には、氏名、所属部署、診断書を提出する旨、休職を希望する期間(診断書記載の期間)、そして休職申請の手続きについてご指示いただきたい旨などを記載します。
診断書を提出した後、会社は診断書の内容を確認し、休職申請の手続きを進めます。会社によっては、休職願や休職届といった所定の書類の提出を求められることもありますので、会社の指示に従いましょう。
休職中の給与や傷病手当金について
休職期間中の経済的な保障は、労働者にとって非常に重要な関心事です。休職中の給与や、公的な給付金制度について理解しておきましょう。
休職中の給与:
多くの会社では、休職期間中の給与は無給となります。これは、休職が労働者の個人的な事由(病気や怪我による療養)によるものであり、労働の提供がないためです。ただし、会社の就業規則によっては、休職開始から一定期間(例:最初の1ヶ月、3ヶ月など)は給与の一部または全額が保障される場合もあります。必ず会社の就業規則を確認してください。
傷病手当金:
健康保険に加入している場合、業務外の病気や怪我による療養のために会社を休み、給与の支払いがない期間について、傷病手当金の支給を受けることができます。傷病手当金は、健康保険組合や協会けんぽから支給される公的な制度です。
傷病手金金の支給要件:
- 業務外の事由による病気や怪我であること: 仕事中や通勤途中の病気や怪我(これは労災保険の対象)ではないこと。
- 療養のために仕事につけないこと: 医師の診断に基づき、療養のため労務不能な状態であること。休職診断書はこの証明となります。
- 連続する3日間を含む4日以上仕事を休んだこと: 待期期間として、連続した3日間(休日を含む)は傷病手当金の支給対象外です。この3日間を「待期期間」と呼びます。4日目以降の休みから支給対象となります。
- 給与の支払いがないこと: 休んだ期間について、会社から給与(休業手当を含む)の支払いがないか、あるいは傷病手当金の額より少ない場合。
支給される期間:
傷病手当金は、支給開始した日から最長1年6ヶ月間支給されます。この期間は、途中で一旦復職して再度休職した場合でも、最初に傷病手当金が支給された日から通算して計算されます。
支給される金額:
支給開始日の以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額の、3分の2相当額が日割りで支給されます。
申請手続き:
- 被保険者記入用: 氏名、期間、振込先口座情報など、本人が記載する箇所。
- 事業主記入用: 会社の担当者が、休んだ期間や給与の支払い状況などを証明する箇所。
- 医師記入用: 医師が、病名、病状、療養期間、就労不能であることなどを証明する箇所。この医師の証明に、休職診断書の内容が反映されます。
傷病手当金の申請期間は、休んだ期間ごとにまとめて行うのが一般的です。会社の担当部署(人事部など)が申請代行をしてくれる場合もありますので、確認してみましょう。
| 経済的保障の種類 | 概要 | 主な財源 | 条件 | 期間/金額 |
|---|---|---|---|---|
| 休職中の給与 | 会社が就業規則に基づき任意で支払う場合がある給与。 | 会社 | 会社の就業規則に定められているか、定められている期間のみ。 | 会社の規定による(多くは無給) |
| 傷病手当金 | 健康保険から支給される、病気や怪我で働けない期間の生活保障給付金。 | 健康保険組合/協会けんぽ | 健康保険への加入、業務外の病気/怪我、療養のための労務不能、待期期間満了。 | 最長1年6ヶ月。過去12ヶ月間の平均標準報酬月額の2/3相当額(日額) |
| 労災保険 | 業務上または通勤途中の病気や怪我の場合に適用される保険給付。 | 労働基準監督署 | 業務遂行性・業務起因性(または通勤災害)が認められること。 | 療養補償給付、休業補償給付など。金額は給与額に基づく。 |
(注:上記の表は一般的なものであり、個別の状況や会社の規定、加入している健康保険の種類によって異なる場合があります。)
休職期間中は収入が途絶える、または減少することが多いため、傷病手当金は貴重な収入源となります。申請手続きを忘れずに行いましょう。
休職期間中の過ごし方
休職期間は、病気や怪我の回復に専念するための大切な時間です。どのように過ごすかが、その後の回復や復職に大きく影響します。
- 治療に専念する: 最も重要なのは、主治医の指示に従い、しっかりと治療に専念することです。処方された薬を正しく服用したり、定期的に通院したり、リハビリテーションに取り組んだりしましょう。
- 十分な休息を取る: 心身ともに疲弊している状態ですので、まずは十分な休息を取り、エネルギーを回復させることが必要です。睡眠時間を確保し、無理のない生活リズムを心がけましょう。
- ストレスを避ける: 休職の原因となったストレス要因から距離を置くことが大切です。仕事のことばかり考えすぎず、会社の人間関係や業務内容に関する悩みから一時的に離れましょう。
- 心身のリフレッシュを図る: 病状が安定してきたら、無理のない範囲で気分転換を図りましょう。散歩をする、趣味の時間を持つ、自然に触れるなど、心身をリフレッシュさせる活動を取り入れます。ただし、過度な活動や旅行などは、主治医と相談してから行うようにしましょう。
- 規則正しい生活を送る: 回復のためには、規則正しい生活リズムを取り戻すことが重要です。毎日同じ時間に寝て起きる、バランスの取れた食事を摂るなど、基本的な生活習慣を整えましょう。
- 会社との連絡: 休職期間中は、原則として業務から離れますが、会社との連絡は必要に応じて行います。主に人事担当者との連絡となり、病状の報告(差し支えない範囲で)、傷病手当金の申請手続き、復職に向けた準備などについてやり取りします。必要以上の連絡や、業務に関する連絡は避けるべきです。
- 復職に向けた準備(後半): 病状が回復し、主治医から復職のGOサインが出たら、徐々に復職に向けた準備を始めます。体力を戻すための軽い運動、通勤経路の確認、生活リズムの調整、リワークプログラムへの参加(後述)などが含まれます。
休職期間中に回復を焦りすぎたり、無理をして活動しすぎると、かえって病状が悪化する可能性があります。主治医の指示を最優先に、自身の体調と向き合いながら、ゆったりと過ごすことを心がけましょう。
休職診断書に関するよくある疑問
休職診断書に関して、多くの人が疑問に思う点や不安に感じる点があります。ここでは、そうしたよくある疑問にお答えします。
診断書があれば必ず休職できる?
結論から言うと、診断書があれば必ず休職できるとは限りません。
診断書は、医師が医学的な見地から就業が困難である、または休養が必要であると証明する書類であり、休職を申請するための重要な根拠となります。しかし、最終的に休職を認めるかどうかは、会社の就業規則に基づいて会社が判断します。
会社が休職を認めない可能性があるケースとしては、以下のようなものが考えられます。
- 就業規則に休職制度がない、あるいは適用条件を満たさない: 会社の規模によっては、休職制度自体がない場合や、勤続年数などの適用条件を満たしていない場合があります。
- 診断書の内容が会社の基準を満たさない: 診断書に記載された病状や休養期間が、会社の定める休職の基準に満たないと判断される場合。
- 会社側の判断: 診断書の内容を考慮した上で、業務への影響や代替要員の確保、会社の経営状況などを総合的に判断し、休職を認められないと判断される可能性もゼロではありません。ただし、従業員の安全配慮義務の観点から、医師が就労不可と判断したにも関わらず就労させることは、会社にとって大きなリスクを伴います。
- 手続き上の不備: 休職申請に必要な書類の提出が遅れたり、会社の指示に従わなかったりした場合。
多くの企業では、医師の診断書が提出され、病状が就業規則に定める休職の条件を満たしていれば、休職は認められるのが一般的です。しかし、「診断書=休職保証」ではないことを理解し、会社の就業規則を事前に確認し、手続きを適切に行うことが重要です。不明な点は、会社の担当者に正直に相談しましょう。
診断書の内容を会社に知られたくない場合
診断書には病名や具体的な症状が記載されるため、会社に自分の病状を詳しく知られることに抵抗を感じる方もいるかもしれません。診断書の内容を会社に知られたくない場合、いくつかの対応策が考えられます。
- 医師に相談する: 診断書を依頼する際に、医師に「会社には病名や詳しい症状を知られたくないのですが、診断書にはどの程度まで記載されますか?」と相談してみましょう。医師によっては、病名は一般的な表現(例:「心身の不調により療養を要する状態」)に留めたり、具体的な症状の記載を控えめにしたり、就労制限の内容を具体的に記載するなど、会社が休職判断に必要な情報に絞って記載してくれる場合があります。ただし、医師は医学的な根拠に基づき正確な診断書を作成する義務があるため、会社が休職判断に必要不可欠な情報の記載を完全に避けることは難しい場合もあります。
- 会社に提出する前に内容を確認する: 診断書を受け取ったら、会社に提出する前に内容をしっかり確認しましょう。もし、会社の知る必要がないと思われる情報(例:過去の病歴、家族構成など)が記載されている場合は、医師に相談して修正してもらえるか確認してみましょう。
- 会社と情報の取り扱いについて話し合う: 会社に診断書を提出する際に、個人情報、特に病状に関する情報について、取り扱いに関する要望を伝えることも有効です。例えば、「診断書の内容は、人事担当者と直属の上司(必要最小限の関係者)のみが確認し、その他の従業員には開示しないように配慮をお願いします」といった要望を伝えることができます。多くの会社では、従業員のプライバシーに配慮し、病状などの機微な個人情報を適切に管理しています。不安な場合は、会社のプライバシーポリシーや個人情報保護に関する規程を確認してみましょう。
- 就労に関する情報に絞る: 会社が休職を判断し、適切な対応を行う上で最も重要な情報は、「現在の病状によって、どの程度の期間、どのような就労が困難か」という点です。病気の根本原因や個人的な背景などは、必ずしも詳細に伝える必要はありません。診断書の内容についても、この「就労への影響」に関する情報が会社にとっては最も重要であることを理解しておきましょう。
ただし、病名や症状の詳細が不明瞭すぎると、会社側が休職の必要性や期間の妥当性を判断しにくくなり、かえって手続きが滞る可能性もあります。医師や会社の担当者とよく相談し、会社が判断に必要な範囲で、かつ自身のプライバシーに配慮された形で情報が伝わるように調整することが大切です。
うつ病の診断書は嘘?虚偽の診断書について
インターネットなどで「うつ病の診断書は簡単にもらえる」「仕事を休むために診断書を偽造した」といった情報を見かけることがあるかもしれません。しかし、うつ病の診断書を偽造したり、実際には病気でないのに医師に嘘をついて診断書を取得したりすることは、絶対にしてはいけない行為です。
虚偽の診断書の問題点:
- 医師法・刑法違反: 医師が真実と異なる診断書を作成することは、医師法に違反する可能性があります。また、虚偽の診断書を公的機関(健康保険組合など)や会社に提出し、不当に利益を得ようとした場合は、詐欺罪などの刑法に問われる可能性もあります。
- 会社との信頼関係の崩壊: 会社に虚偽の診断書を提出したことが発覚した場合、会社との信頼関係は完全に崩壊します。これは懲戒処分の対象となり、解雇される可能性が非常に高いです。
- 傷病手当金などの不正受給: 虚偽の診断書で傷病手当金を申請し、不正に受給した場合、返還を求められるだけでなく、詐欺罪などで逮捕される可能性もあります。
- 自身の心の問題: 本当は別の問題を抱えているのに、休職のためにうつ病などの診断書を「利用」しようとすることは、自身の心の問題を解決しないまま先延ばしにすることになります。
うつ病などの精神疾患は、外見からは分かりにくいため、「嘘をついて診断書をもらえるのではないか」と考える人もいるかもしれません。しかし、医師は問診や診察、各種検査などを通じて、総合的に患者の精神状態や病状を判断します。安易に嘘をついても、医師は専門家ですので見抜く可能性が高いです。
本当に体調が悪く、仕事の継続が困難である場合は、正直に医師に相談し、適切な診断と診断書の発行を依頼しましょう。病気でないのに休みたいという場合は、年次有給休暇を取得したり、会社に相談して働き方を見直したりするなど、別の方法を検討すべきです。
虚偽の診断書は、自分自身の信用を失墜させるだけでなく、法的な問題や経済的な損失につながる、非常にリスクの高い行為です。
休職から復帰するまでの流れ
休職はあくまで治療の一環であり、最終的な目標は回復して職場に復帰することです。休職期間中の過ごし方や、復帰に向けた準備が重要になります。
復職に向けた準備と会社の面談
休職期間が終わりに近づき、主治医から復職可能であるという判断が出たら、徐々に復職に向けた準備を始めます。同時に、会社側も復職に向けた手続きを進めます。
復職に向けた労働者側の準備:
- 規則正しい生活リズムの確立: 休職中に崩れてしまった生活リズム(起床・就寝時間、食事時間など)を、会社の勤務時間に合わせて整えます。
- 体力の回復: 体力が低下している場合があるため、軽い運動(ウォーキングなど)から始め、徐々に体を慣らしていきます。
- 通勤のシミュレーション: 実際に会社の最寄駅まで行ってみる、通勤時間帯に公共交通機関を利用してみるなど、通勤の負担を確認します。
- 仕事に関するウォーミングアップ: 復職後にスムーズに業務に入れるよう、関連書籍を読んだり、簡単な資料作成の練習をしたりするなど、無理のない範囲で仕事に関連する活動を再開します。
- 主治医との復職相談: 復職可能かどうか、復職にあたって会社にどのような配慮が必要か(例:残業制限、業務内容の調整、時短勤務など)について、主治医と詳細に相談します。主治医から「復職可能である」という診断書や意見書を発行してもらう必要があります。
会社の復職手続きと面談:
- 復職願の提出: 労働者側から会社に復職を希望する旨を記した「復職願」またはそれに準ずる書類と、主治医の「復職可能」である旨の診断書(または意見書)を提出します。
- 会社の産業医面談(または医師の意見聴取): 会社の規模によっては、産業医との面談が義務付けられています。産業医は、主治医の診断書や労働者の状況を踏まえ、医学的な見地から復職の可否や就業上の配慮の必要性を判断し、会社に意見を述べます。産業医がいない会社の場合は、主治医の意見書に基づき、会社が判断したり、必要に応じて医師の意見を聴取したりします。
- 人事担当者・上司との面談: 産業医や医師の意見、そして本人の希望を踏まえ、人事担当者や復職先の部署の上司と面談を行います。面談では、復職後の配属先、業務内容、勤務時間、残業の有無、体調に関する配慮事項などについて話し合います。この面談を通じて、会社は復職支援計画を策定します。
- リハビリ出勤・試し出勤制度: 病状によっては、いきなりフルタイムで働くのが難しい場合があります。会社によっては、短時間勤務から始めたり、週に数日だけ出勤したりする「リハビリ出勤」や「試し出勤」といった制度を設けていることがあります。これらの制度を活用することで、段階的に職場に慣れることができます。
これらの手続きや面談を通じて、本人、主治医、会社(人事、産業医、上司)が情報を共有し、協力して安全かつ円滑な復職を目指します。
リワークプログラムの活用
特にメンタルヘルスの不調による休職の場合、回復して職場に復帰するためのリハビリテーションとして、リワークプログラムを活用することが有効な場合があります。
リワークプログラムとは:
リワーク(Rehabilitation for Work)プログラムは、休職している人が職場復帰するために、生活リズムの調整、心身の安定、ストレス対処スキルの習得、集中力や作業能力の向上などを目的とした専門的なリハビリテーションプログラムです。医療機関、地域障害者職業センター、民間のリワーク支援施設などで実施されています。
プログラムの内容(例):
- 生活リズムの調整: 規則正しい生活習慣を確立するための指導。
- 心理療法・カウンセリング: ストレス対処法、認知行動療法、集団療法など。
- 作業療法・運動療法: 集中力、持続力、体力向上を目指すプログラム。
- 模擬業務・職場環境調整の練習: 実際の業務に近い環境での作業練習や、職場でのコミュニケーション練習。
- 復職支援セミナー: 復職後の注意点、再発予防に関する知識の習得。
リワークプログラムのメリット:
- 段階的なリハビリ: 専門家のサポートを受けながら、無理なく復職に向けた準備を進めることができます。
- 自信の回復: プログラムを通じて作業能力が回復したり、ストレスへの対処法を学んだりすることで、復職への自信を取り戻すことができます。
- 再発予防: 病気への理解を深め、ストレス対処スキルを身につけることで、復職後の再発リスクを減らすことが期待できます。
- 客観的な評価: プログラムへの参加状況や課題への取り組みを通じて、本人の回復度や復職可能かどうかの客観的な評価を得ることができます。これは、会社が復職を判断する上でも参考になります。
リワークプログラムへの参加は任意ですが、特に休職期間が長期にわたる場合や、職場復帰に不安がある場合に、主治医や会社の担当者と相談の上、活用を検討してみる価値は大きいでしょう。費用やプログラムの内容は施設によって異なりますので、事前に確認が必要です。地域障害者職業センターは公的な機関であり、無料で利用できるプログラムも提供しています。
まとめ:休職診断書が必要な場合は早めに相談を
病気や心身の不調により仕事を続けることが困難になった場合、休職は心身を回復させるために必要な選択肢です。そして、休職には医師の診断書が重要な役割を果たします。
診断書は、病気や怪我によって就業が困難であることを医学的に証明し、会社が休職を判断し、期間を決定し、必要な手続きを進めるための根拠となります。多くの会社では、休職申請に診断書の提出を義務付けています。
休職診断書を取得するためには、まずは医療機関を受診し、医師に現在の病状と仕事への影響、そして休職を検討している旨を正直に相談しましょう。特にメンタルヘルスの不調の場合は、精神科や心療内科を受診し、症状を具体的に伝えることが重要です。診断書には病名、病状、就労への影響、必要な休養期間などが記載されますが、会社に提出する前にその内容を確認し、必要に応じて医師や会社の担当者と相談することが大切です。診断書の発行には費用がかかり、一般的には自費診療となります。
休職期間中は、会社の就業規則に基づく期間が設定され、病状によっては延長も可能ですが、会社の定める上限があります。休職期間中は治療に専念し、傷病手当金などの公的な制度を活用して経済的な不安を軽減することも重要です。
休職期間が満了に近づいたら、主治医と復職の可否について相談し、会社との面談やリハビリ出勤などを経て復職を目指します。特にメンタルヘルスの場合、リワークプログラムの活用も有効な選択肢となります。
もし、現在体調が悪く、休職を検討している場合は、一人で悩まず、まずは早めに医療機関を受診し、医師に相談することをお勧めします。そして、会社の就業規則を確認し、人事担当者や上司にも相談してみましょう。適切な手続きを踏み、必要な診断書を取得することが、心身の回復とスムーズな休職、そしてその後の復帰への第一歩となります。
免責事項: 本記事の情報は一般的な内容に基づいており、個別の状況や会社の規定、法制度の詳細については異なる場合があります。休職や診断書に関する具体的な手続きや制度については、必ずご自身の会社の就業規則や人事担当者、加入している健康保険組合にご確認ください。また、病状に関するご判断は、必ず医師にご相談ください。