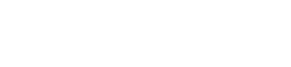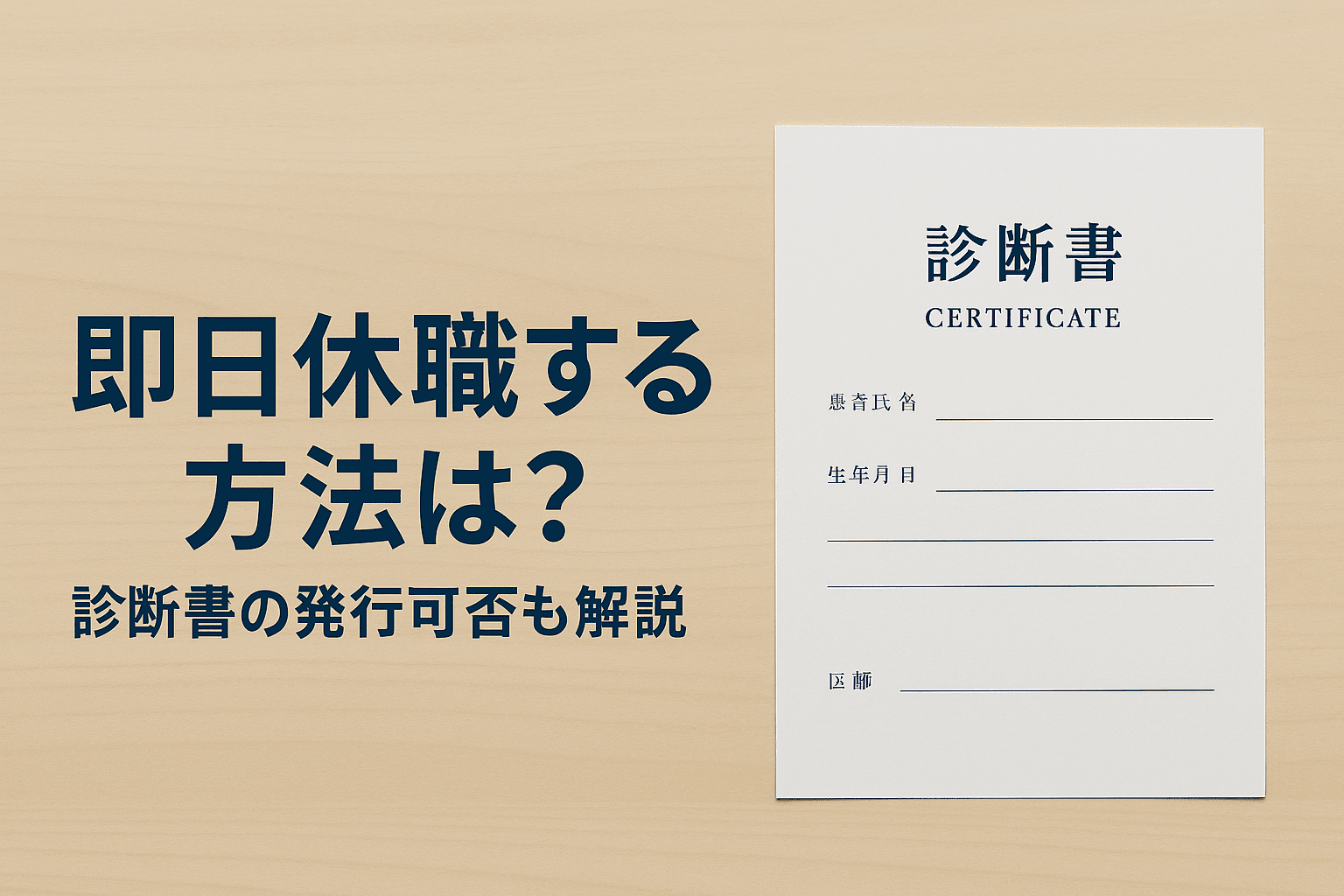精神的な不調や体調不良が続き、「もう会社に行くのがつらい」
「今すぐにでも休んで回復に専念したい」と感じている方もいるかもしれません。
休職を検討する際に必要となるのが、多くの場合、医師による診断書です。
特に、今すぐ休職したいと考えている方にとって、「診断書を即日発行してもらえるのだろうか?」という点は大きな不安要素となるでしょう。
この記事では、休職に必要な診断書が即日発行される可能性について詳しく解説し、即日発行を目指すための具体的なステップや、診断書以外に必要な手続きについてもご紹介します。
今のつらい状況から一歩踏み出し、心身を回復させるために、まずは専門家への相談を検討してみましょう。
結論から言うと、休職のための診断書が即日発行される可能性はゼロではありませんが、常に可能というわけではありません。
診断書の即日発行が可能かどうかは、受診する医療機関の方針、医師の判断によって即日対応してくれるクリニックもあります!
オンライン診察おすすめクリニック

| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| 予約 | LINEで簡単予約 24時間受付 |
| 診断書 | 〇 当日発行対応 |
| お薬 | 〇 初診から処方 |
| 診察料 | 3,850円~ |
| 実績 | 10万件越え |
\即日の休職相談ならメンクリで/
診断書即日発行が可能なケースとは
比較的、診断書の即日発行の可能性が高いと考えられるのは、以下のようなケースです。
- 緊急性の高い病状の場合: うつ病による強い希死念慮がある、パニック発作が頻繁に起こり外出が困難、重度の不眠で日常生活に著しい支障が出ているなど、患者さんの安全確保や早急な休養が不可欠と医師が判断した場合。
- 症状が非常に明確で、短時間の診察でも診断が可能と医師が判断した場合: 例えば、特定のストレス原因によって急激に体調を崩した適応障害など、比較的診断がつきやすい病状の場合。
- 以前から同じ医療機関に通院しており、病状の変化を医師が把握している場合: 継続して同じ医師の診察を受けており、病状が悪化し休職が必要になったことを医師がすぐに理解できる状況。
- 医療機関が診断書の即日発行に対応している方針の場合: クリニックによっては、緊急性の高いケースに限り、または特定の条件を満たす場合に即日発行に対応していることがあります。ただし、これはあくまで医療機関の方針によるため、事前の確認が必要です。
即日発行が難しいケースとその理由
一方で、診断書の即日発行が難しい、あるいは不可能であるケースも多くあります。
- 診断に時間がかかる場合: 症状が複雑で、複数の要因が絡み合っている場合、あるいは身体的な病気との鑑別が必要な場合など、正確な診断を下すために時間をかけて診察したり、追加の検査が必要になったりすることがあります。初診では、患者さんの状態を把握しきれないと医師が判断する場合もあります。
- 医師が初診での診断書発行に慎重な場合: 医師によっては、患者さんの状態をより正確に判断するために、複数回の診察を通じて経過を観察してから診断書を発行する方針を取っている場合があります。これは、診断書の重みを理解し、責任を持って発行するための方針であり、患者さんの不利益になるわけではありません。
- 医療機関の予約状況や体制: 受診希望者が多く、医師の診察時間が限られている場合や、診断書作成の事務手続きに時間がかかる場合など、医療機関側の体制によって即日発行が物理的に難しいことがあります。
- 患者さんの希望する休職期間が長い場合: 長期間の休職診断書は、医師にとってより慎重な判断が求められます。そのため、初診でいきなり数ヶ月単位の休職診断書の発行を希望しても、医師は一旦短期間での診断書を発行し、経過観察とする場合があります。
このように、診断書の即日発行は保証されたものではありません。
しかし、適切な準備と医師への正確な情報提供を行うことで、即日発行の可能性を高めることは可能です。
ステップ1:心療内科・精神科を受診する
休職の原因が精神的な不調である場合、心療内科または精神科を受診することが最も適切です。
これらの専門医は、心の病気に関する専門的な知識と経験を持っており、あなたの症状を正確に診断し、適切な治療や休職に関するアドバイスを行うことができます。
内科などでも診断書を発行してもらえることがありますが、精神的な不調に関しては専門医の受診をお勧めします。
受診前の準備しておくべきこと
診察時間を有効に使い、医師に正確な情報を伝えるためには、事前の準備が非常に重要です。
- 現在の症状を具体的にメモする:
- 精神的な症状: ゆううつな気分、不安、イライラ、集中力の低下、意欲の低下、何事にも興味が持てない、落ち着かない、死にたい気持ちなど。いつから、どんな時に強く出るか。
- 身体的な症状: 眠れない(寝つきが悪い、途中で目が覚める、早く目が覚める)、食欲不振、全身の倦怠感、動悸、息苦しさ、頭痛、めまい、腹痛、肩こりなど。これらの症状が、仕事にどのように影響しているか。
- 症状が出始めた時期と経緯: いつ頃から体調が悪くなったのか、何かきっかけがあったのか。症状がどのように変化してきたのか。
- 仕事に関する具体的な困難を整理する:
- 業務内容: どんな業務で困難を感じているか(例: 会議で発言できない、メール返信に時間がかかる、簡単な計算ミスが増えたなど)。
- 人間関係: 職場での人間関係に問題があるか。具体的なエピソード。
- 労働環境: 残業時間、休日出勤、ハラスメントなど、仕事環境に問題があるか。
- これらの困難によって、どのように仕事に支障が出ているか(例: 業務効率が著しく低下した、遅刻や欠勤が増えたなど)。
- 休職したい理由と希望期間を整理する: なぜ休職したいのか(例: 十分な休息が必要、治療に専念したい、環境を変えたいなど)。どれくらいの期間休職したいと考えているか(例: まずは1ヶ月、可能であれば3ヶ月など)。ただし、希望期間はあくまで目安として伝え、最終的な期間は医師の判断に委ねる姿勢が重要です。
- これまでの病歴や治療歴: これまでに精神的な病気やその他の病気にかかったことがあるか。現在服用している薬(他の科で処方された薬、市販薬、サプリメントなども含む)があれば、お薬手帳や薬剤情報提供書を持参しましょう。
- その他: 家族構成、生活状況、経済状況、飲酒・喫煙習慣など、医師の診断に役立つ情報があればまとめておきましょう。
これらの情報を事前に整理しておくことで、診察中に伝え漏れを防ぎ、医師があなたの状態をより正確に理解する助けとなります。
症状や困りごとを具体的に話すことが、診断書発行の判断材料となります。
即日対応可能なクリニックの探し方・選び方
診断書の即日発行を希望する場合、事前にクリニックの情報を収集することが重要です。
- クリニックのウェブサイトを確認する: 多くのクリニックでは、ウェブサイトに診療方針や診断書発行に関する情報を掲載しています。「診断書」「休職」といったキーワードで検索してみましょう。ただし、「即日発行します」と明記しているクリニックは少ないかもしれません。
- 直接クリニックに問い合わせる: これが最も確実な方法です。電話で問い合わせる際に、「休職のために診断書が必要なのですが、初診で即日発行していただくことは可能でしょうか?」と正直に尋ねてみましょう。ただし、医師の判断によるため確約はできない旨を伝えられることがほとんどです。「緊急性が高い場合であれば、医師の判断により当日発行の可能性もあります」といった回答が得られるかもしれません。
- オンライン診療の活用: 近年、オンライン診療を導入している心療内科・精神科が増えています。オンライン診療でも診断書の発行は可能ですが、即日発行が可能かどうかはクリニックによって異なります。また、初診でのオンライン診療には制限がある場合もありますので、必ず事前に確認が必要です。オンライン診療は、自宅から受診できるため、体調が悪くて外出が難しい場合や、近くにクリニックがない場合に有効な選択肢となります。
- 口コミや評判を確認する: インターネット上の口コミサイトなどで、そのクリニックの対応や診断書発行に関する情報がないか確認してみるのも一つの方法です。ただし、個人の感想であるため、鵜呑みにせず参考程度にとどめましょう。
- 予約の取りやすさ: 即日受診・即日発行を希望する場合、予約が取りやすいかどうかも重要な要素です。ウェブサイトや電話で当日の予約状況を確認しましょう。
重要なのは、「即日発行できるクリニック」を探すというよりは、「即日発行の可能性について相談できるクリニック」を探すという視点を持つことです。
そして、たとえ即日発行が難しくても、自身の状態を適切に診察してもらい、今後の対応について医師と相談することが最も大切です。
ステップ2:医師に現在の状況と希望を伝える
診察が始まったら、事前に準備したメモを見ながら、現在の症状や仕事での困難、休職したい理由などを、正直かつ具体的に医師に伝えましょう。
- 症状の重篤さを具体的に伝える: 例えば、「ゆううつで何も手につかない」「毎日眠れず、体が鉛のように重い」「仕事中に急に息苦しくなり、どうにかなってしまうのではないかと思う」など、具体的なエピソードを交えて話すと、医師はあなたの苦痛をより深く理解できます。
- 仕事への影響を具体的に伝える: 「以前は難なくこなせた業務ができなくなった」「遅刻や欠勤が増えてしまった」「同僚とのコミュニケーションが全く取れなくなった」など、仕事に支障が出ている具体的な状況を伝えましょう。
- 休職したいという希望を明確に伝える: 診断書発行の目的が休職であることを医師に伝えましょう。「現在の状況では仕事を続けることが難しく、休職して療養に専念したいと考えています」と、休職が必要だと感じる理由を説明します。
- 即日診断書発行を希望する理由を伝える: 緊急性が高いと感じている場合は、その理由を伝えましょう。「これ以上仕事を続けると、自分の心身がもたないと感じる」「すぐにでも休んで、心身を回復させたい」など、切実な気持ちを伝えましょう。ただし、無理強いするような態度は避け、医師の判断を尊重する姿勢が大切です。
医師は、あなたの話を聞き、診察を通じて医学的な判断を行います。
正確な情報提供を心がけ、医師との信頼関係を築くことが、適切な診断と診断書発行に繋がります。
ステップ3:診断書の発行手続き
医師が診察の結果、休職の必要性を認め、診断書を発行することになった場合、発行の手続きを行います。
診断書の発行にかかる時間と費用
診断書の即日発行が可能と医師が判断した場合でも、診察後すぐに受け取れるとは限りません。
診断書の作成には、医師が病状や休養期間などを記載し、署名・押印する作業が必要です。
外来が混雑している場合などは、書類作成に時間がかかることがあります。
受付で「〇時頃に取りに来てください」あるいは「郵送します」と言われることもありますので、確認しましょう。
診断書の発行にかかる費用は、医療機関によって異なりますが、健康保険は適用されません。
自由診療となるため、費用は医療機関が自由に設定できます。
一般的な相場は、3,000円~10,000円程度です。
事前にクリニックのウェブサイトで料金を確認するか、受付で尋ねておくと安心です。
診断書の内容について
休職診断書には、一般的に以下の内容が記載されます。
| 項目 | 記載される内容 |
|---|---|
| 傷病名 | 医師が診断した病名(例: 適応障害、うつ病、うつ状態など) |
| 症状 | 現在の主な症状や状態(例: 抑うつ気分、不眠、意欲低下、食欲不振、全身倦怠感など) |
| 発症年月日 | 病気が発症したと考えられる時期 |
| 必要な休養期間 | 医師が医学的に必要と判断した休養期間(例: ○年○月○日~○年○月○日、約○ヶ月間など) |
| 治療上の指示 | 休職の必要性、自宅療養の指示、通院の必要性など。回復のためのアドバイスが記載されることもあります。 |
| その他 | 病状によっては、職場での配慮事項などが記載されることもあります。 |
| 医師の署名押印 | 発行年月日、医療機関名、所在地、医師の氏名、署名、押印 |
診断書の内容は、医師があなたの病状に基づいて判断するため、希望通りの内容にならない場合もあります。
特に、希望する休養期間については、医師が回復の見込みなどを考慮して判断します。
会社への連絡・報告
診断書を取得したら、速やかに会社に連絡し、休職したい旨を報告しましょう。
- 誰に連絡すべきか: 直属の上司や人事担当者に連絡するのが一般的です。会社の就業規則で定められている場合もあるので、確認しておきましょう。
- どのように連絡すべきか: 電話、メール、会社の規定で定められたシステムなど、適切な方法で連絡します。メールで連絡する場合は、現在の状況を簡潔に伝え、診断書を取得したこと、休職を希望していることを明記しましょう。口頭での報告だけでなく、後から確認できるよう書面やメールなどの形で記録を残しておくことが重要です。
- 診断書提出のタイミング: 診断書は、会社の指示に従って提出します。多くの場合、休職願や休職届と併せて提出を求められます。提出方法は、手渡し、郵送、メール添付(会社による)などがあります。
会社の担当者と具体的な休職開始日や手続きについて相談し、指示に従いましょう。
休職願・休職届の提出
多くの会社では、休職する際に「休職願」や「休職届」の提出を求めています。
- 会社の規定確認: 会社の就業規則や人事規定で、休職の手続きについて確認しましょう。書式の指定がある場合もあります。
- 提出書類: 一般的に、休職願(または休職届)に診断書を添えて提出します。会社によっては、別途書類の提出を求められることもあります。
- 記載内容: 休職願には、氏名、所属部署、休職理由(病気療養のためなど)、休職希望期間などを記載します。
これらの書類を提出することで、会社があなたの休職を正式に承認し、休職期間中の取り扱い(給与、社会保険、復職基準など)が決定されます。
傷病手当金の手続き
休職期間中は給与が支払われないか、減額されることが一般的です。休職中の生活費を保障する制度として、健康保険から傷病手当金が支給される場合があります。
- 傷病手当金とは: 健康保険に加入している会社員などが、病気やケガで会社を休み、給与の支払いを受けられない場合に、標準報酬日額の約3分の2が支給される制度です。支給期間は、支給開始日から最長1年6ヶ月です。
- 手続きの流れ: 傷病手当金の申請には、健康保険の被保険者、事業主(会社)、医師のそれぞれの証明が必要です。
- 健康保険組合(または協会けんぽ)から申請書を入手する。
- 申請書の「被保険者記入用」欄に必要事項を記入する。
- 申請書の「事業主記入用」欄を会社に記入してもらう。
- 申請書の「療養担当者記入用(医師の意見書)」欄を医師に記入してもらう。
- 全ての記入が完了したら、健康保険組合(または協会けんぽ)に提出する。
- 申請期間: 労務不能であった期間ごとに申請します。通常、1ヶ月ごとや数ヶ月ごとにまとめて申請します。療養のため労務不能となった日を含め、4日以上連続して休んだ場合に、4日目から支給対象となります。
- 必要書類: 傷病手当金支給申請書の他、医師の意見書、会社の証明書、診断書(写し)などを求められることがあります。
傷病手当金の手続きは、休職中の貴重な収入源となります。
手続きが煩雑に感じるかもしれませんが、会社の担当部署(人事部など)に相談すれば、手続き方法を教えてもらえるはずです。
\初診から診断書発行対応/

| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| 予約 | LINEで簡単予約 24時間受付 |
| 診断書 | 〇 当日発行対応 |
| お薬 | 〇 初診から処方 |
| 診察料 | 3,850円~ |
| 実績 | 10万件越え |
\即日の休職相談ならメンクリで/
最初の診断書で書かれる期間
心療内科や精神科の医師が初めて休職診断書を発行する場合、最初の休職期間は比較的短く設定されることが多いです。
これは、患者さんの病状が今後どのように変化するかを見極めるため、また、治療によってどれくらい回復するかを予測するためです。
- 一般的な最初の期間: 2週間~1ヶ月程度と診断されることが多いです。
- 期間設定の理由: 短期間で一度病状を再評価し、治療の効果や今後の見通しを立てるため。また、患者さん自身も「まずはこの期間休もう」という目標を持ちやすくなります。
この最初の期間で病状が回復すれば、そのまま復職となります。
しかし、十分な回復が得られない場合は、休職期間の延長が必要になります。
休職期間を延長する場合
最初の診断書に記載された休職期間が終了しても、まだ復職できる状態ではない場合は、休職期間の延長が必要となります。
- 再診の予約: 休職期間が終了する前に、必ず再度主治医の診察を受けましょう。
- 病状の報告: 再診時に、休職中の病状の変化や現在の体調などを医師に報告します。
- 延長の判断: 医師が診察の結果、休職の継続が必要と判断した場合、診断書を再発行してもらいます。この診断書には、延長後の休職期間が記載されます。
- 会社への手続き: 会社に休職期間延長の旨を連絡し、再発行された診断書を提出します。会社所定の延長手続きが必要な場合もあります。
休職期間が合計でどのくらいになるかは、会社の就業規則で上限が定められている場合があります。
ご自身の会社の規定を確認しておきましょう。
また、傷病手当金の支給期間も最長1年6ヶ月であるため、それ以上の休職が必要な場合は、別の支援制度の検討が必要になります。
病状の回復には個人差があり、焦りは禁物です。
医師とよく相談し、ご自身のペースで回復を目指しましょう。
診断書なしで休む方法はある?
診断書がない場合でも、会社を休むことは可能です。
- 有給休暇の取得: 残っている有給休暇を取得して休むことができます。
- 欠勤: 診断書がない「欠勤」扱いとなる場合もあります。ただし、無断欠勤は会社の懲戒処分の対象となる可能性があるため、必ず会社に連絡し、許可を得る必要があります。病気による欠勤であることを伝え、医師の診断書は後日提出する旨を相談しましょう。
- 会社の特別休暇制度: 会社によっては、傷病による特別休暇制度を設けている場合があります。会社の規定を確認してみましょう。
診断書なしで休む場合、会社への説明や評価への影響など、一定のリスクが伴う可能性があります。
できる限り、医師の診断を受けて、適切な形で会社に報告することが望ましいです。
しかし、緊急でどうしても休む必要がある場合は、まずは会社に連絡し、状況を説明して指示を仰ぎましょう。
別の医療機関を探す
もし受診したクリニックで即日診断書の発行が難しかった場合でも、すぐに諦めずに別の医療機関を探すことも選択肢の一つです。
ただし、むやみに複数の医療機関を受診すること(いわゆるドクターショッピング)は、却って診断を混乱させたり、医師からの信頼を得にくくしたりする可能性もあります。
- 冷静に状況を判断: なぜ即日発行が難しかったのか、医師の説明をよく理解しましょう。医師が「まずはじっくり診察したい」と考えた場合は、その判断に従うことも大切です。
- 別の医療機関を探す際の注意点: どうしてもすぐに診断書が必要なやむを得ない事情がある場合は、事前に電話などで「初診で即日診断書発行の可能性について相談したい」旨を明確に伝えてから受診を検討しましょう。ただし、繰り返しになりますが、即日発行を保証する医療機関はないことを理解しておく必要があります。
- 今のクリニックでの治療を続ける: 診断書発行は難しくても、そのクリニックの医師が信頼でき、継続的な治療を受けたいと感じるのであれば、そのまま治療を続け、医師とよく相談しながら休職のタイミングを検討することも重要です。
最も大切なのは、あなたの心身の健康です。
焦らず、ご自身にとって最善の方法を選択しましょう。
休職を検討するサイン・目安
どのような状態になったら休職を検討すべきなのでしょうか。
以下のようなサインが続く場合は、休職を検討する一つの目安となります。
- 身体的なサイン:
- 原因不明の体調不良(頭痛、腹痛、吐き気など)が続く
- 疲れが取れない、全身の倦怠感が強い
- 眠れない、あるいは寝すぎてしまう
- 食欲がない、あるいは過食になってしまう
- 動悸、息切れ、めまいなどが頻繁に起こる
- 精神的なサイン:
- ゆううつな気分が毎日続き、何も楽しめない
- 強い不安感や焦燥感を感じる
- 集中力や判断力が著しく低下する
- 些細なことでイライラしたり、怒りっぽくなる
- 無気力になり、身だしなみや家事がおろそかになる
- 人と会いたくない、引きこもりがちになる
- 死にたい、消えてしまいたいといった気持ちが頭をよぎる
- 行動面のサイン:
- 遅刻や早退、欠勤が増える
- 仕事でミスが増え、業務効率が著しく低下する
- 周囲とのコミュニケーションがうまくいかなくなる
- 趣味や好きなことへの関心がなくなる
- 飲酒量や喫煙量が増える
これらのサインは、心身がSOSを出している可能性が高いです。
「気のせいだろう」「もう少し頑張れば回復するはず」と我慢せず、早めに専門機関に相談することが大切です。
診断書はいつからもらえますか?
初診の診察で、医師が必要と判断すれば、その日から診断書を発行してもらえる可能性はあります。
ただし、これは医師の判断と病状によります。
症状が軽く、休職の必要性が低いと判断された場合や、診断に時間を要する場合は、初診での発行が難しいこともあります。
まずは受診して、現在の状態を医師に正確に伝えることが第一歩です。
診断書をもらえないことはありますか?
はい、診断書をもらえないこともあります。
以下のような場合が考えられます。
- 病状が診断書の必要レベルに至らないと医師が判断した場合: 医師の診察の結果、休職が必要なほどの病状ではないと判断された場合。
- 医師が初診での診断書発行に慎重な方針の場合: 患者さんの状態を複数回診察して判断したいと考える医師の方針による場合。
- 虚偽の申請や、診断書発行を強要するような行為: 正直な情報提供を行わない場合や、無理に診断書発行を迫るような行為は、医師との信頼関係を損ない、診断書発行が難しくなります。
診断書はあくまで医学的な判断に基づいて発行されるものです。
医師の判断に従いましょう。
適応障害で休職する場合、診断書は必要?期間は?
適応障害で休職する場合も、会社への提出書類として診断書が必要となるのが一般的です。
適応障害は、特定のストレス原因(職場環境、人間関係など)によって心身に不調をきたす病気です。
休職期間は、ストレス原因から離れることで比較的短期間で改善が見られる場合もあれば、長期化する場合もあり、個人差が大きいです。
最初の診断書では1ヶ月~3ヶ月程度の休養期間が記載されることが多いですが、病状によっては延長が必要になることもあります。
復職時期は、症状の改善度合いを見ながら、医師と会社と本人が話し合って決定します。
「休職 即日」というキーワードで検索するほど、あなたは今、切羽詰まった状況にいるのかもしれません。
すぐにでも会社を休んで回復に専念したいという気持ちは痛いほど分かります。
休職のための診断書が即日発行される可能性は、あなたの病状や受診する医療機関によって異なります。
しかし、最も大切なのは、今のつらい状況を放置せず、心療内科や精神科といった専門家へ相談することです。
医師に正直に症状を伝え、適切な診断とアドバイスを受けることが、心身を回復させるための第一歩です。
診断書の即日発行が可能かどうかは医師の判断に委ねられますが、適切な準備をして受診に臨むことで、スムーズな手続きにつながる可能性を高めることができます。
一人で抱え込まず、まずは専門医のドアを叩いてみましょう。
あなたの健康が何よりも大切です。
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の治療法や医療機関を推奨するものではありません。個別の診断や治療については、必ず医師や専門家の判断を仰いでください。記事内の情報は記事作成時点のものであり、法制度や医療情報等は変更される可能性があります。